2006年7月、ポツダム。この歴史的に重要な街で、2006年のPCEは開催されました。
PCEは、Person-Centered and Experiential Psychotherapy and Counselingの略。つまり来談者中心療法の学会です。
ヨーロッパでPCAが最もさかんなのはイギリスなので、参加者はイギリス人が最も多かったのは当然ですが、次に参加者が多いのは驚くべきことに日本人でした。九産大大学院から大挙して押しかけたこともこれには貢献しています。その他、ドイツなどヨーロッパ諸国のほか、少数ですがアメリカ、アルゼンチンといった世界各国の参加者とともに、まる1週間をすごしました。個人的には、楽しかったけど、文化の違いについて考えさせられた学会でした。
以下はその体験記として、2006年度の九州産業大学臨床心理センター紀要に掲載したものです。原題は、『ソーセージ文化とフィッシュ文化−PCE2006に参加して』です。
****************************************
「私の名前、日本語だとディッシュ(皿)になるらしいわね。英語じゃプリンセスなのよ。」話しかけてきたのは、イギリス人のSarahだった。学会前行事のエンカウンターグループが終了する頃にはなんとなく、積極的に異文化交流したほうがいいというムードができあがっていた。Sarahと私は昼食後、学会行事をさぼって木陰で話をすることになった。
Sarahは40歳過ぎらしいが、快活で若く見えた。二人きりになるとすぐに、「スピリチュアリティってわかる?」と聞いてきた。私が、「日本では最近、水曜の夜に霊媒の出るテレビ番組が放映されているから、スピリチュアリティが一般人に知られてきている。」と言うと、Sarahはたいそう喜んだ。イギリスはそういうもののメッカであるらしい。「イギリスでは毎日、median(霊媒)のTV番組があるわ。それから、スピリチュアルチャーチというのがあって、関心のある人は週末の午前中、そこに行くのよ。スピリチュアリティソング、知ってる?」Sarahは歌ったが、私はさすがにそこまでは知らなかった。「賛美歌よ。歌い終わったらmedianの話を聞くの。medianがみんなの周りを歩きながら、『あなたのお母さんが今ここに(守護霊として)来ていますよ』といったことを語っていくのよ。私は前世が武将で、戦いの人生だったんですって。そんな自分を赦すためにも今世産まれてきたんだ、とmedianに言われたわ。」
そんなたわいのない(?)話の合間に、Sarahは言った。「私の父は戦争に行ったの。ドイツが戦争をしたせいよ。父は戦車を運転していたから、直接人殺しの役割ではなかったけど、どうしても戦車で人を踏み倒さないといけない場面があったの。」英語が不自由な私のためにSarahは戦車の絵を描きながら、父の過去が自分の体験であるかのように顔をしかめた。「それが傷になったのね。戦争から帰ってきた父は、硬くて、打ち解けない人になってしまったの。父が本来の父のままであったら、私や、私の家庭はもっと違っていたはずよ。だから私はドイツをずっと許してなかったわ。許す気持ちになったのは、ほんの5年前。さっきのエンカウンターグループで何人かの人が、ドイツを許せないと言っていた気持ちは分かるわ。きっと、怒りもプロセスで、そこを通り越せてはじめて、許すところに行くのだと思うわ。」
私はSarahの話を聞いて、ヨーロッパ人の戦争に対するとらえ方に、日本人との違いを感じた。ヨーロッパ人は今でも、当時敵国であった国の人に、複雑な感情を持っている。戦争が自分に与えた影響を具体的に意識化し、「戦争がなかったらこうだったはずだ」というイメージをはっきり持っている。ヨーロッパ大陸が多くの国の集合体だからかもしれない。敵国の人がすぐとなりにいて、家系的にも民族が混じりあっている中では実際、戦争の影響を意識せずにはいられないだろう。ソーセージの皮の中にみっちりと、多様な民族の歴史と今が詰まっている。ヨーロッパはそんな場所だ。
Sarahは私に、日本人はアメリカ人に対してどういう感情を持っているのかと聞いた。私は話した。「日本人はアメリカをかつての敵国として強く意識しているわけではない。敗戦直後からアメリカの文化が入ってきて、憲法もアメリカの指示で作られ、日本人がその内容におおむね満足したからだと思う。反面、日本はアメリカを頼らなくては生きて行けない国になった。始終アメリカの顔色を伺っている。特に軍事力の面でアメリカに頼っているから、アメリカ人を憎んで遠ざけることができない。そういう構造だから日本人は、アメリカ人への怒りを意識化することなく時が過ぎている。日本では戦争についての喪のプロセスが、ある部分は進み、ある部分は留まったままになっているかもしれない。」Sarahは私の言うことを理解したようだった。
私の親族も明らかに戦争で苦労したはずだが、祖母や父母などから戦争の話は聞いたことがない。私の父も打ち解けない人で、親しく父と話した記憶はないが、その原因について私が戦争のせいかもしれないなどと思ってみたことはそれまで全くない。「父が子ども時代に戦争に遭わず、無邪気に育っていたら、本来の父はどんな人だったのだろう」…。私がもっと、そんなことに思いを馳せていたら、家族の関係はもしかしたら、違ったものになっていたかもしれない。
学会はパーソンセンタードの人ばかりということもありフレンドリーで、私が怪し気な英語で四苦八苦しゃべっていると外国人が一人また一人と集まってくるので気が抜けない。事例好きのヨーロッパ人は、他人がどういう状況で生きているか聞くことが好きらしく、休憩時間に日本の状況をさまざまに質問してくる。
カウンセリングが普及しているイギリスでは、開業していれば医師からクライエントを紹介され、スクールカウンセラーをしていれば教師が生徒を一人一人カウンセリングルームに寄越してくるという具合で、カウンセラーは座っていればクリニックスタイルの純粋な面接ができるらしい。日本のスクールカウンセラー達が校内を巡回したりして関係づくりに気を使っている様子はたいへん新鮮に写るらしく、日本の臨床に関する九産大院生の発表もたいへん好評だったようだ。ほー、とかへー、と言いながら、異文化の話を楽しんで聞いてくれていたヨーロッパ人だが、一つだけ、特にイギリス人がムキになってくる話題があった。それはスーパービジョンについてだった。
「スーパービジョンは義務づけられているわ。個人で週1回スーパービジョンを受けるでしょ、それとは別にスクールカウンセラーのグループスーパービジョンがあるの。面接は全部録音して、逐語にしてスーパービジョンを受けるのよ。日本もそう?」年輩のイギリス人女性がそう尋ねるので、私が「個人やグループでのスーパービジョンは日本にもありますが、面接を録音することはほとんどありません。日本ではカウンセリングが十分に一般的ではないこともあり、カウンセラーはカウンセリングを気軽だと感じてもらうために気を遣うのです。日本人のクライエントは録音をとられることに敏感ですから。」そうと言うと、野蛮人を見つけたというかのようにイギリス人達がわんさか集まってくる。
「なぜ録音しないの。スーパービジョンはカウンセラーの技術向上に必要なもので、そのために録音は欠かせないのだというと、拒否するクライエントはいないわよ。日本人は、ちゃんとクライエントに説明しているの?」「そう言われればそうですが、テープがなくても記録で十分ですし、カウンセラー側の感じを見つめる作業もあるのですから、スーパービジョンはそれで十分だと私は感じています。」イギリス人は、噛んでふくめて教え諭すような口調になって、「逐語がないと、本当のところが分からないでしょう。カウンセラーが肝心なところに気づかないままになってしまうわ。逐語を使ったスーパービジョンをするべきよ」再三話の結論がここに来るのには参った。
たしかに、今の日本のカウンセラーが、面接の録音をクライエントに打診すらしてないと言われればそうだ。でも、もしテープが取れたとして、何か目覚ましいメリットはあるだろうか。
ヨーロッパ的な臨床では、逐語を使ったスーパービジョンは必要なものなのかもしれない。ヨーロッパのパーソンセンタードの事例を聴くと、第一人者のそれは、深く二人の人間が出会って結晶を凝縮させていくようなセラピーだ。スーパービジョンもきっと徹底したもので、セラピストが自分の人格に向き合うように行われるに違いない。その上で実現する、クライエント?セラピストの関係性の深さ、クライエントが自分を見つめていく作業の深さ。魅力的だけれど、そのような「深さ」を日本のカウンセリングで実現しようとしたらどうなるだろうか。私がスーパーバイジーに対してヨーロッパ的なスーパービジョンを続け、バイジーがそんなスーパービジョンを反映させたようなセラピーをしたら、どういうことになるだろうか。それは日本の中で良い臨床だと言えるだろうか。
いろいろ言いたいことはあったがヨーロッパ人に伝えることができなかった。ソーセージを食べながら、それを伝えることは無理だと思った。おいしい。たしかにおいしい。肉も血も脂も複雑なスパイスも、全部皮の中に閉じ込めて凝縮し、チップでスモークしたソーセージは、間違い無く世界で一番おいしい食品だ。彼等ヨーロッパ人が言う面接やスーパービジョンとは、きっとこのソーセージのようなものなのだ。そもそも彼等にとって、この人生を一人の人間として生き抜くことは、人生早期からの記憶、家系全体、歴史、前世、−自分という皮袋の中に入っているすべてのものを意識化し、そのブレンドを見つめて味わいつくすことなのだ。
だけど、負け惜しみを言うようだが、ここの魚料理ときたらどうだろう。コートレットやムニエルの、衣の内側に、魚の旨味も魚が住んでいた川の匂いも「全部閉じ込めて」焼いてある。日本的な魚料理−適度な塩を降りかけて余計な水分と臭みを出し、風味のポイントを残そうという発想は、ここにはない。
ヨーロッパ料理が足し算なら、日本料理は引き算。塩のほどよさに命をかける…、そう、どう「ほどよく」あるか、常に気づかっている日本のカウンセラーたち。
日本ではきっと、深さだけが求められているわけではない。 そこのところが、伝わる日は来るのだろうか。いや、そう簡単には来ないだろう。だってドイツのソーセージは、これはこれで比類なくおいしく、完結しているものなのだから。
****************************************
以上、雑感でした。PCEは2008年、イギリスで開催予定です。これから九産大の院生になられる方で、興味のある方は、また、大挙してイギリスを訪れることになるでしょう。
ちなみに、ヨーロッパ人は事例が大好きですから、学会発表は事例でなさることをお勧めします。

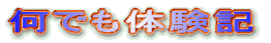
PCE2006体験記

